- コラム
- 猫研究所
2025.05.01
猫の爪切りの頻度は?適切な頻度や安全な切り方のコツを解説[#猫研究所]
![猫の爪切りの頻度は?適切な頻度や安全な切り方のコツを解説[#猫研究所]](../../../../ext/magazine/images/10087_00035_1.jpg)
猫の爪は獲物を捕らえる武器だったり、壁をよじ登ったりする際に使われます。
なかには、私たちの体をよじ登って肩などに乗ってくる子も。しかし、その際に爪が体に食い込み、痛い思いをしたことがある人は多いのではないでしょうか。
今回は、猫の爪切りの適切な頻度や安全な切り方のコツについて、ゴロー研究所のスタッフ猫たちの意見も交えながらご紹介します。

猫の爪切りが必要な理由
猫の爪切りは、猫や私たち家族のケガを防止したり、家具や柱などがボロボロにならないように、適切な頻度で行う必要があります。
猫自身の怪我を防ぐため
猫の爪が伸びたままの状態だと、猫が家具やカーテンを引っかいた際に引っかかってしまい、無理に取ろうとして爪を怪我してしまう可能性があります。
また、伸びっぱなしの爪が猫の肉球に刺さったりすると、猫がケガをしてしまうのです。
家族の怪我を防ぐため
猫に引っかかれると、私たち家族も傷口から感染し病気を発症してしまう可能性があります。
「猫ひっかき病」や「パスツレラ症」といった感染症にかかってしまうと、発熱や頭痛、肺炎などを引き起こしてしまうこともあるため、猫の爪切りは定期的に行っておくことが望ましいと言えます。
■ 猫の爪とぎの目的は?
一方で、「猫は爪とぎをしているから爪切りは不要だろう」と考えられる人は多くいらっしゃるのではないでしょうか。
一見爪とぎでも問題ないと思われがちですが、爪とぎは古くなった爪をはがして、新しい爪を露出することが目的です。
爪とぎでは爪の先端は削れないため、先述の理由から定期的に爪を切る必要があります。


-
ゴロー
爪が肉球に刺さるのでありますか!?ボクちんのぷにぷにの肉球に鋭い爪が刺さったらとっても痛そうであります…

-
王子
犬に比べて猫の爪はカーブしやすいから、円を描くように伸びて先端が肉球に刺さりやすいのだ。
特にシニアの猫は、爪とぎする頻度が減って爪が分厚くなりやすいから、家族がこまめに爪の伸びすぎをチェックしてあげてほしいのだ。
猫の爪切りの頻度

猫の爪切り
猫の爪切りの頻度については、爪が伸びるスピードが異なるため下記のように子猫・成猫・シニア猫で異なります。
こちらでは、それぞれの期間における猫の爪切りの頻度をご紹介します。
子猫の場合
子猫は成長期であることなどから、爪も早く伸びる傾向に。そのため、1~2週間に1回を目安に切ってあげましょう。
まだ爪を上手にしまうことができず、家具やカーテンなどに引っかかりやすいため、こまめに切ってあげることでケガの予防にもつながります。
成猫の場合
生後1年以上経過している成猫であれば、2~3週間に1回程度を目安に爪を切ってあげましょう。
猫の体調や活動量によって爪が伸びるスピードは異なるため、こまめに爪の状態を確認することが重要です。
シニア猫の場合
シニア猫は爪とぎの頻度が少なくなる子が多く、古い爪がはがれずに残っていることがあるため、こまめにチェックしながら、2週間に1回を目安に切ってあげましょう。
爪とぎの回数が減っている場合、爪が適切に削れず、古い爪が残ることで爪が巻き込まれてしまうことがあります。
爪が伸びすぎると、爪が肉に食い込んでしまったり、爪が折れて感染症を引き起こしたりするリスクが高まります。
また、爪とぎをしないことでストレスが溜まり、行動面でも問題が発生することがあるため、不安があれば動物病院に相談することをおすすめします。
爪切りに必要な道具
猫の爪を切る際には専用の爪切りが必要になりますが、大きく分けてハサミタイプとギロチンタイプに分けられます。
ハサミタイプは持ちやすく、狙いを定めやすいので初めての場合でも扱いやすいでしょう。
ギロチンタイプの爪切りはハサミタイプよりも力が伝わりやすく、硬い爪を切るときにおすすめです。
爪を切る際のステップ

爪を切る際のステップ
猫の爪は、下記の手順で進行しましょう。
ステップ.1
まずは猫が落ち着けるように、膝の上にのせる、横に寝かせる、タオルで包むなどの姿勢を探しましょう。
複数人で爪を切る際には、猫を抱っこしてもらい、おやつを与えて猫の気をそらすことができます。
爪切りについては初めての場合はハサミタイプのもの、慣れてきたら短時間で切りやすいギロチンタイプのものにする、というのもひとつ。
爪が小さくて細い子猫の場合は、ハサミタイプの方がおすすめです。
ステップ.2
姿勢が定まったあとは、前足を触られると嫌がる猫が多いため、後ろ足から爪を切っていきましょう。
肉球を軽く押して爪を出し、ピンク色に透けて見える血管の先端から2~3mmを目処に切ります。
誤って血管を切ってしまうと猫に痛みを与えてしまうため、ギリギリを狙わず余裕を持って切ることがポイントです。
ステップ.3
爪切りが終わったあとは、猫に「爪切りは良いことがある」イメージを持ってもらうために、おやつやおもちゃを与えましょう。
爪きりに良いイメージを持ってもらうことで、次回以降の爪切りがスムーズになります。
一方、血管を傷付けてしまうとトラウマになってしまい、爪切りを嫌がってしまうため注意が必要です。


-
ゴロー
みんなは爪切りについてどう思うでありますか?

-
ナナ
あたちは抱っこ大好きだし、爪切りの時は家族がおひざの上でぎゅ~としてくれるからうれしいな♪
でも、おててのところでパチンッて音がするのは苦手なの~

-
ムー
わたしは抱っこされるのも、爪をむにゅっと出されるのも好きじゃないわ。
健康のために必要みたいだから我慢してあげるけど、終わったらちゃんとゴージャスなご褒美がほしいわね。

-
ランラン先生
猫が爪切りを嫌がる理由をまとめると「爪を押し出される行為」「爪切りの音や衝撃」「拘束時間の長さ」などになりますね。
基本的に猫は自分の思うままに自由にしていたい生き物。爪を切る際のステップをしっかりと頭に入れて、なるべく短時間でスムーズに爪切りできるといいですね。
爪を切る際の注意点
爪を切る際は、下記のポイントに注意しましょう。
暴れている場合
結論として、爪切りを嫌がっている猫の爪を無理やり切ろうとするとケガのリスクが高くなるため、無理に行う必要はありません。
私たち家族との関係性が悪化する可能性も考えられるため、猫が落ち着くまで待つことをおすすめします。
出血した場合の対処法
誤って血管まで切ってしまい、指先から出血が見られたときは、清潔なコットンで5分程度圧迫しながら猫の様子を観察しましょう。
指先を圧迫しても止まらない場合は、家族間で判断せずに動物病院に相談することが大切です。


-
ランラン先生
爪切りの時に猫が暴れる場合は、洗濯用ネットや猫用のマスクを使って視界を隠してあげると、落ち着いてくれることもあります。
もしもおうちでの爪切りが難しい場合は、動物病院で爪切りしてもらう選択肢もありますので、無理をしないようにしてくださいね。
おわりに
今回は、猫の爪切りについて解説しました。
猫の爪切りは、猫や私たち家族のケガ・病気を防止する、家具がボロボロになるのを防ぐために行う必要があります。
子猫1~2週間に1回、成猫は2~3週間、シニア猫は2週間に1回を目安として切ってあげましょう。
爪を切る際は落ち着ける姿勢を探し、後ろ足から切り始めて最後はおやつやおもちゃを与えて、爪切りのイメージを良くします。
暴れているときは落ち着くまで待ち、誤って血管を切った際はガーゼで止血して圧迫、止まらなかった場合は動物病院に相談しましょう。


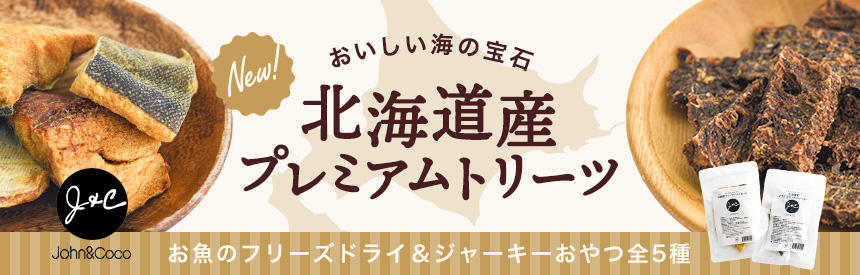




![猫の腎臓病新薬「AIM薬」ついに年内実用化へ[#獣医師監修]](../../../../ext/magazine/images/aim2026_main.jpg)
![猫と人間の違い【睡眠編】猫はなぜそんなに眠るのか?人間とは違う「睡眠の仕組み」を進化から読み解く[#猫研究所]](../../../../ext/magazine/images/sleep202601_main.jpg)
![猫の留守番は何日まで?必要なアイテムと健康・安全対策を解説[#猫研究所]](../../../../ext/magazine/images/cat-sitting-at-home_main.jpg)







![猫と人間の違い【感情編】喜怒哀楽のかたち〜猫と人間の「気持ち」のしくみを探る〜[#猫研究所]](../../../../ext/magazine/images/cat-emotions_main.jpg)
![猫の冬の健康対策|寒さで起こる症状と予防法を徹底解説[#猫研究所]](../../../../ext/magazine/images/neko-fuyu-kenko-yobou_main.jpg)
![猫と人間の違い【共生編】 なぜ肉食獣の猫は人間と暮らせるのか?[#猫研究所]](../../../../ext/magazine/images/cat-symbiosis_main.jpg)
![猫の水分補給を促す方法とおすすめフード~猫たちと学ぶ、飲まない理由と飲ませ方[#猫研究所]](../../../../ext/magazine/images/cats-promotes-hydration_main.jpg)
